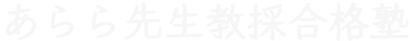教員採用試験の場面指導どう対策する?評価ポイントや回答のコツも解説!
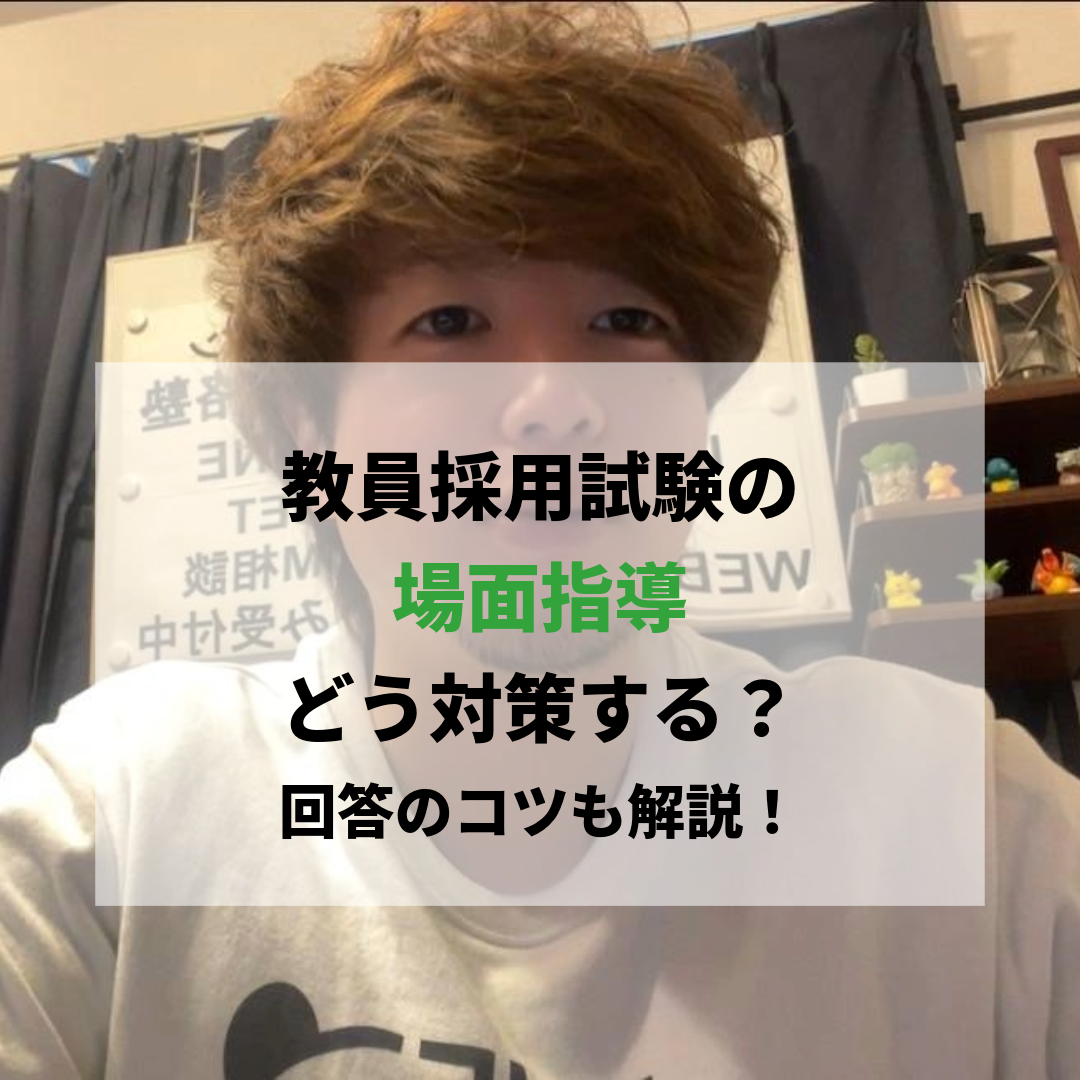
教員採用試験における「場面指導」は、教育現場で起こりうる具体的なトラブルや課題に、どのように対応できるかを問われる試験です。
授業中における生徒への対応や、保護者によるクレームなど、実際に起こり得る状況に対して自分の言葉で冷静かつ現実的な対応策を伝える必要があります。
この記事では、場面指導の評価ポイントやよくある質問への回答例、高評価につながる対策のコツを詳しく解説します。
場面指導で自信をもって対応できるよう、具体的な準備を進めていきましょう。
教員採用試験の場面指導とは?評価ポイントも解説
教員採用試験の「場面指導」とは、教育現場で直面する具体的な教育的課題やトラブルに対し、適切に対応できるかを評価する試験です。下記のように授業中・業務中に起こりうる様々なシチュエーションにおける問題が出題され、その場で対策方法や意見を述べる必要があります。
「授業中に生徒が突然泣き出したらどうする?」
「保護者から理不尽なクレームが来たらどうする?」
「同僚と意見が対立した場合はどう対処するか?」
場面指導は主に一人または複数の試験官と面接形式で実施され、制限時間は1〜5分程度です。場面指導では、主に下記のポイントが評価されます。
- 状況に応じた的確な判断ができているか
- 子どもや保護者・同僚への配慮があるか
- 教師としての倫理観や責任感が伝わるか
- 言葉遣いが丁寧で論理的に説明できているか
- 冷静かつ柔軟に対応できているか
現場をイメージし、冷静かつ誠実な対応を心がけることが重要です。
教員採用試験の場面指導でよくある質問と解答例
教員採用試験の場面指導でよくある質問を下記3ジャンルに分けて解説します。
- 児童・生徒指導に関する質問
- 保護者対応に関する質問
- 教員同士の連携に関わる質問
それぞれ回答例も紹介します。場面指導の質問における傾向や回答のヒントを見つけましょう。
児童・生徒指導に関する質問
場面指導では「授業中に突然泣き出す生徒がいた場合、どう対応するか?」といった質問がよく出題されます。まずは落ち着いて児童・生徒の様子を見守り、周囲の児童にも配慮しつつ、必要に応じて本人を教室の外などで丁寧に声掛けするなどの対応が求められます。
【解答例】「まずは本人の気持ちを尊重し、静かな場所で話を聞きます。授業に影響を出さずに本人の両立を図ります。」
保護者対応に関する質問
場面指導では「保護者から一方的なクレームを受けた場合、どうするか?」という質問もよく出題されます。まず相手の話を最後まで聞き、事実を確認したうえで冷静に対応する姿勢が重要です。
【解答例】「まずは相手の話を聞く勢を大切にしつつ、事実を丁寧に確認します。自分だけで抱え込まず、状況によっては学年主任と相談します。」
自分の感情で意見を語ろうとせず、必要に応じて周囲とも連携しながら対応を進める姿勢をアピールしましょう。
教員同士の連携に関わる質問
「同僚教員と指導方針が異なるとき、どう対応するか?」といった質問も、場面指導でよく出題されます。他教員との連携に関する質問では「児童生徒にとって何が最善か」を軸にした意見を述べる姿勢が重要です。
【解答例】「まずは相手の考えを尊重しながら、自分の意見も冷静に伝えます。児童にとってより良い方向を模索し、対話によって共通認識をつくるよう努めます。」
他教員との連携に関する質問への回答では、同僚とのコミュニケーションを重視する姿勢が求められます。理想論ばかり語るのではなく、周囲との協調性を重視した回答を心がける姿勢が大切です。
教員採用試験の場面指導対策のコツ
教員採用試験の場面指導対策におけるコツは、大きく分けて下記6つです。
- 指導のゴールを決めておく
- 話が長くなりすぎないよう注意する
- 子どもにどのような考え方・行動の仕方になってほしいのかを決める
- いつどのような状況で指導するのか決める
- 子どもに質問しながら考えさせる
- 子どもの味方でいることを意識する
それぞれ意識すべきポイントも紹介します。
指導のゴールを決めておく
場面指導では、「どんな考え方や行動を身につけてほしいのか」といった最終的なゴールを明確にしておくことが大切です。問題行動への対処そのものだけでなく、その後の子どもの成長を見据えた対応が求められます。
「約束を守る大切さを理解させたい」などといった具体的な目標があると、回答に一貫性が出て説得力が増します。行き当たりばったりで回答をするのではなく、事前に指導のゴールを決めておくのがおすすめです。
話が長くなりすぎないよう注意する
本番では限られた時間で回答しなければならないため、話が長すぎると内容が逸脱してしまうリスクが高まります。長々と意見を述べるのではなく、面接官との会話のキャッチボールを意識しましょう。
自分の意見を結論から伝え、エピソードや根拠を端的に補足する「PREP法」などを活用すると、話を簡潔にまとめやすくなります。話している途中で伝えたいことを見失わないよう、話す内容を事前に構造化しておく練習が重要です。
子どもにどのような考え方・行動の仕方になってほしいのかを決める
場面指導では「何がダメだったか」だけでなく「今後どうしていけば良いか」を子どもに気づかせる視点が求められます。
将来的に「どのような価値観や行動を子どもに育んでほしいのか」を事前に明確にしておきましょう。「相手の気持ちを想像できるようになってほしい」「我慢する力を身につけてほしい」など、具体的な目標を頭の中で言語化しておきましょう。
いつどのような状況で指導するのか決める
場面指導では、子ども一人ひとりに対して「いつどのような状況で指導するか」を決めておく必要があります。子どもへの声かけや指導は、タイミングや場所によって効果が大きく変わります。
同じ内容でも授業中に注意するのか、それとも授業後に個別に話すのかで効果が変わります。「他の子どもの前ではなく、静かな環境で個別に意見を聞く」など、子どもの心情に配慮した指導の流れを組み立てましょう。
子どもに質問しながら考えさせる
場面指導では、子どもとの質疑応答の中から答えを導き出す工夫も大切です。一方的に意見を述べるのではなく、子ども自身に「なぜその行動をとったのか」「どうすればよかったか」を考えさせましょう。
なかなか意見を言わない子どもに対しては「どうしてそう思ったのかな?」「今度はどうしたらいいと思う?」といった質問を通じて、主体性を育む取り組みが求められます。
子どもの味方でいることを意識する
場面指導では「教師は子どもの味方であること」を忘れないようにしましょう。そもそも指導は叱ることが目的ではなく、子どもがより良い方向に成長するために必要な過程のひとつです。
たとえ子どもを叱るときも「あなたを責めたいわけではない」といった姿勢を態度や言葉で伝えることが重要です。子どもが「この先生は自分のことを理解してくれている」と感じられるような寄り添い方を意識しましょう。
教員採用試験の場面指導に関してよくある質問
最後に、教員採用試験の場面指導に関してよくある下記の質問へ回答します。
- 場面指導の対策にロールプレイは必須?
- 場面指導の質問への回答でウソをついてもよい?
- 場面指導で面接官の反応が薄かったら不合格のサイン?
ここまで触れていない内容についても、参考情報として目を通しておきましょう。
場面指導の対策にロールプレイは必須?
場面指導の対策にロールプレイは必須ではないものの、非常に効果的な対策方法の一つです。実際の試験における流れを把握するためには、言葉の選び方や表情、声のトーンまで実践的に意識することが大切です。
接客関連の仕事経験が少ない方にとっては、具体的な対応イメージを身につけるための練習手段となるでしょう。
場面指導の質問への回答でウソをついてもよい?
教員採用試験の場面指導においては、ウソの内容であっても「理想の教師像を語る」「まだ経験していないことを仮定して話す」こと自体は問題ありません。しかし、明らかに実現困難な対応や、現場感覚が乏しい内容だと評価が下がる可能性もあります。
質問への回答では、話に一貫性があり現実的な意見を述べることを意識しましょう。
場面指導で面接官の反応が薄かったら不合格のサイン?
場面指導の試験において面接官の表情や相槌が少なくても、それが不合格のサインとは限りません。面接官の中には受験者の意見にあまり反応を示さず、公平に評価するためにあえて無表情で対応する人もいます。
面接官のリアクションの有無に一喜一憂せず、最後まで落ち着いて自分の考えを伝えましょう。目先の目標に対して焦りすぎず、聞かれている内容に誠実かつ論理的に答えることが大切です。
教員採用試験の場面指導では「具体性と寄り添う姿勢」がカギ
教員採用試験の場面指導では「具体性」と「子どもに寄り添う姿勢」が欠かせません。どれだけ理想的なことを話しても、実際の現場でどう行動するかが伝わらなければ意味はないので注意しましょう。
面接官への回答時には、単に「生徒に寄り添う」と言うだけでなく「話を聞いたうえで具体的な対応をどうするか」まで示すことが大切です。事前によくある質問を把握しておき、ロールプレイを通して自分の言葉で伝えられるよう準備しましょう。
教員採用試験の場面指導対策には「あらら先生教採合格塾」がおすすめ
教員採用試験の場面指導対策には「あらら先生教採合格塾」がおすすめです。
あらら先生教採合格塾では、神奈川県川崎市で教員経験を持つ代表・こいずみあきら氏が「教員試験絶対受からせる人」として日々生徒の教育・コーチングに励んでいます。
試験合格に向けた勉強方法やマインドセットに関する配信が毎日行われているので、日々の学習を仕組み化したい方にも向いています。
来年の教員採用試験に合格したい方は、あらら先生教採合格塾の公式ラインをチェックしましょう。